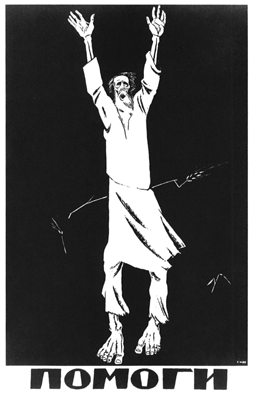
長縄さんがマーティン・メイリアというバトンをもって力走し、僕はそれを受けて継走しなければならない。幸いにも、メイリアの『ソヴィエトの悲劇』( 草思社、1997年) の導入部「はじめに――歴史的問題点 審判の時」は、『コメンタリー』誌でのメイリアによるパイプスのロシア革命研究への書評と、その重要な論点において同じである。(M. Malia, The Hunt for the True October. Commentary, 1991 October, Vol.92, No.4)
僕は最近の数年間をパイプスの『ロシア革命史』(成文社より近刊、 A Concise History of the Russian Revolution. New York, 1995)の翻訳にたずさわってきた。その余勢をかって、中年の知に――この知が病に冒され痴と化しているのを懼れているのだが――鞭打って騎士然として颯爽と継走を果たさなければならない。このリレーが継走であり、エッセイが試論をも含意するとすれば、気は少し軽く安らぐ。
僕は、まずロシア革命と20世紀を同時代として生きた諸々の碩学のなかにパイプスという一人の研究者をおくことから始めたい。
20世紀を生きその同時代を知的な研究対象とした研究者たちのなかで、E. H. カー(1892-1982) は、日本の知識人に大きな影響を及ぼしてきた人物の一人である。彼の業績とロシア革命論については、『ロシア革命 レーニンからスターリンへ 1917-1929年』( 塩川伸明訳、岩波書店、2000年)とそれに付した溪内謙の優れた解説を参照されたい。ここで、溪内氏は、カーを冷戦的思考から超然とした学問的態度を評価しつつ、「かつて歴史を支配し「崩壊」とともに解体したスターリン主義正統に代わったのは、歴史の政治からの解放ではなく、歴史的想像力を欠いた冷戦的思考としてカー氏が退けていた全体主義論という新しい正統であった」と、述べている。パイプスがこの「全体主義論という新しい正統」の主唱者の一人であることは、論を俟たない。カーはこの著作の最終章「歴史的展望の中の革命」を、レーニンの四月テーゼから始め、「ロシア革命は最初から混血児的で両義的な性格をもっていた」と確認する。そして、この「混血児的で両義的な」ロシア革命のスターリン体制への移行は、「党と国家の共同の権威によって課された「上からの革命」のカテゴリーに属する」とし、レーニンからスターリンへの移行を問題とする。彼は、「革命の最初の半世紀の惨禍がすべて、国内的要因あるいは、スターリン独裁の鉄の手に帰せられるわけではない」とし、「体制の厳しさと残酷さは現実のものであった。しかし、その成果もまた現実のものだったのである」と、ソヴェト体制の「残酷さ」と「成果」をともに確認するのである。この最終章は次のように結ばれている。
「一九一七年のロシア革命は、それが自らに課した目標と、それが生み出した希望の実現にははるかに遠い。その記録は欠陥をはらみ、両義的である。しかし、それは、近代のいかなる歴史的事件よりももっと深く、もっと持続的な反響を世界に及ぼしている源なのである。」
イギリス外交官として戦間期を生き、「両義的な」評価に巧みなカーが「父」の世代とすると、エリック・ホブズボーム、ロイ・メドヴェージェフ、そしてリチャード・パイプスは「子」の世代にあたる。この三人は、ロシア革命後の戦間期から第二次大戦に青春を迎えた世代である。
ホブズボームは、1917年にエジプトのアレクサンドリアに、ロシア系ユダヤ人を父とし、オーストリア人を母として生まれている。ウィーンとベルリンで育ち、ナチスドイツの雰囲気を肌で感じつつ、1933年 1月にベルリンの「その日の午後に」新聞の見出しでヒトラーの首相就任を知るのである。やがてイギリスに渡り、西欧左翼の論客として、日本の知識人にも大きな影響を与えることになる。彼の近著『20世紀の歴史 極端な時代』( 河合秀和訳、三省堂、1996年) では、ロシア革命は「短い20世紀」の通奏低音のように響いているのである。
この著作で、ホブズボームがロシア・ソ連の歴史に関して依拠した文献は、M. Lewin, A. Nove, R. W. Davies, Sh. Fitzpatrick といった修正派とマルクス主義者の研究である。彼は「冷戦の神話」によって、レーニンがクーデターの組織者とされることに対して、「真の論点は、反共の歴史家が主張しているように、それ [十月革命] が レーニンによる基本的に反民主主義的な一揆ないし、クーデターであるかどうかではなく、誰が、あるいは何が、臨時政府の次の政権になるべきであったか、また成り得たかということだ」と断言する。その第二章「世界革命」のなかで、彼はフランス革命が19世紀にとってもった意義と同じく、20世紀の歴史にはロシア革命が重要な出来事となったと確認し、「一言でいえば、短い20世紀の歴史は、ロシア革命のその直接、間接の影響を抜きにしては理解できないであろう」と、この章を結ぶのである。
ロイ・メドヴェージェフは、1925年にグルジアのトビリシに生まれている。父の粛清をうけ、スターリン批判後はソ連の反体制知識人として知られることになる。彼の『1917年のロシア革命』( 現代思潮社、石井・沼野監訳、1998年) は、パイプスとの対話を基調として読むことができる。この著作の序文で、ロシア革命がフランス革命より重大であったとするパイプスが紹介される。しかし、彼の立場は、パイプスとは対蹠的である。日本語版への序文で、「ロシア史と世界のあらゆる左翼的社会主義運動の歴史をよりよく理解するために」と、その意図を示し、「ロシア革命がもたらした結果のすべてを疑問視することは、無益かつ非現実的であろう」と自らの立場を示すのである。彼は、「ボリシェヴィキが1917年に夢想した世界革命の形ではないが、社会主義への転換は世界でなお起きている。この転換は多くの点でロシア革命の影響を受けて起きている」と考えるが、ここには、ロシア革命とその後のソ連体制を全否定するパイプスとは際立った対照がある。メドヴェージェフは、パイプスのロシア革命論の摘要である『ロシア革命をめぐる三つのなぜ』( モスクワ、1996年) と対話しつつ、パイプスの示す論点を触媒としながら、それへの同意と反発を織り込みながら論を進めているのである。炯眼な読者は、この対話に気付かれるであろう。
20世紀を同時代として生き、ロシア革命と知的に格闘してきたこれらの碩学に比して、パイプスは日本の読者に知られることが少なかった。彼は、第一次大戦後の1923年にポーランドのチェシンに生まれ、ロシア革命が生み出した緊迫した状況とナチスの台頭にみられる戦間期の国際情勢のなかで育ち、1939年にポーランドを襲った危機のなかで、イタリアへ偽造パスポートで逃れている。さらに、スペイン、ポルトガルを経て、1940年 7月にアメリカに向かう。このスリリングなヨーロッパ脱出行については、すでに邦訳の「訳者あとがき」に述べた通りである。第二次大戦後、彼はアメリカの学界において全体主義論が形成されるなかで、優れた一連の歴史研究を世に問うことになる。
さて、パイプスの研究の特徴をいくつかの点で摘記しておく必要があろう。社会主義に親和的で「両義的な」カー、反スターリン主義の「異論派」メドヴェージェフ、イギリスのマルクス主義者ホブズボームと異なって、パイプスの政治哲学は保守的自由主義であり、ソ連論は全体主義論を枠組みとしている。彼の研究は、1960年代半ば以降、西側で隆盛をほこった「修正主義者」への批判と、彼と同じ全体主義論のなかにあるメイリアとの対比を通じて、その特徴と方向性がより具体的、鮮明に浮上してくるように思える。
まず、パイプスが論考 "1917 and the Revisionists". The National Interest, No.31(1993, Spring) で体系的な「修正主義者」批判を展開していることに注目しなければならない。ここでは、修正派の登場が1960年代の社会史やアナール派の研究に胚胎するものとされ、その主要な論点が指摘されている。十月をプッチではなく「人民蜂起」と捉え、「全体主義」という概念を斥け、「下から」の視点から政治とイデオロギーをないがしろにしていると、指摘するのである。パイプスは、「十月は権力を独占しようとする党のプッチ」であることを強調し、修正派が「政治」を重視しないことを厳しく批判するのである。
この「政治」を復権させる動きのなかで、つまり、溪内氏の指摘をかりれば「新しい正統」として「全体主義論」が擁護されているのであるが、パイプスとメイリアの立場が異なることにも留意しなければならない。メイリアの『ソヴィエトの悲劇』は、解説を寄せた長谷川氏も指摘するように、修正主義派とともにパイプスのロシア論にも「矢を向けている」のである。パイプスが「家産制」という概念を用いて、ツァーリズムとソ連体制の連続性をみつつ、全体主義を論じるのに対し、メイリアは歴史的な断絶と社会主義というイデオロギーを中心に据えて、ソ連体制を全体主義として論じるのである( 彼の「ソヴィエティズム」論) 。近刊の『ロシア革命史』のなかで、パイプスが全体主義論を擁護しつつ、「家産制」を歴史分析のキー概念としていることは明らかである。彼によれば、マルクス主義のイデオロギーが家産制に接ぎ木され、全体主義が生まれたのである。彼は、その最終章「ロシア革命への省察」で次のように述べる。
「イデオロギーは重要であるが、しかし、共産主義ロシアの形成におけるその役割は過大視されてはならない。……イデオロギーは副次的な要因とみなされねばならない。それは、恐らく、新しい支配階級の着想と思考様式ではあるが、支配階級の行動を決定したり、それを子孫に説明するところの一揃いの原則ではなかったのである。一般的に、ロシア革命の実際の経過について知るところが少なければ、それだけマルクス主義者の理念に支配的な影響があったとみなしがちである。」
これはメイリアへの批判の文として読めるが、全体主義論における「ロシア史を欠いたソヴェト学」を批判するロバート・タッカーは、この点でパイプスに親和的である。彼は「エタティズム」の立場からソヴェト体制を論じ、パイプスの論じるニコライ一世の警察国家に「プロト= 全体主義の型」を読み取る。その点で、タッカーは、パイプスの研究を評価するのである。(R. Tucker, "Sovietology and Russian History". Post-Soviet Affairs, Vol.8, No.3, 1992)
メイリアの自らの全体主義論とパイプスのロシア革命論への批評は、彼の次の二つの論考に窺える。"A Fatal Logic". The National Interest, No.31(Spring, 1993): "The Hunt for the True October". Commentary, Vol.92, No.4(October, 1991). ところで、この二人の全体主義論の含意するところを、チャールズ・フェアバンクスが的確に指摘している。彼は、パイプスの研究にみられる啓蒙主義への厳しい判定と、ヒューム、バーク、テーヌといった思想家の革命の拒否という伝統の彼による継承をとくに挙げている。Ch. H. Fairbanks, "Lessons from the Soviet Collapse". Commentary, Vol.98, No.3(September, 1994). 啓蒙主義への批判、カント、ポッパーらの目的と手段に関する古典的論議、そして近代の革命への批判的考察は、パイプスの『ロシア革命史』の基調をなしており、ここには、西欧近代に深く根づく彼の保守的自由主義の政治哲学が窺えるのである。
最後に、ソ連と冷戦構造の崩壊のなかで「一人勝ち」し、超然たる "Super Power" を誇るアメリカ、そこでのパイプスの論調と傾向にふれておきたい。
パイプスは "Russia's Past, Russia's Future". Commentary, Vol.10, No.6(June, 1996) と題した論考のなかで、ソルジェニーツィンらのネオ・スラヴ派に批判を放っている。ソルジェニーツィンは、1980年に、G. ケナン、R. タッカーとともにパイプスを、彼らが革命前のロシアと共産主義時代を連続的にみていると非難し、両者を厳密に区別することを求めていた。ソルジェニーツィンに対し、ネオ・スラヴ派がロシアの問題はマルクス主義にあり、それが西からもたらされた「ウイルス」であり、ロシアに根をもたないと考えていると、パイプスは批判する。彼は、M. ウェーバーのいう「家産制」の遺産を強調して応える。同時に、共産主義は「単なるイデオロギー」ではなく、一党支配、警察テロル、生産資源の国家独占、出版と教育の全面的な統制、信仰の抑圧などが組み合わされた複合的な現象であると主張する。ここでは、「崩壊」後のネオ・スラヴ派のみならず、メイリアのイデオロギーからの説明を含め、ロシアの歴史断絶論への批判を読みとることができよう。
東欧革命とソ連「崩壊」のなかで一躍もてはやされた F. フクヤマの「歴史の終焉」論、さらにS. ハンチントンの「文明の衝突」論に対しても、パイプスはコメントを怠らない。前者の楽観性、後者の西側の文明に本質的な要件、つまり、パイプスに言わせると私的所有とそれに随伴する政治的自由と経済成長への理解を欠いた悲観論、これらを指摘しながら、彼は両者の間に自らを位置づけている。(Commentary, Vol.103, No.3, March, 1997.)
さて、ロシア革命の研究は、カーの「父」の世代、ヨーロッパの辺境から現れた三人に代表される「子」の世代、そして、我々の世代と継承されてきた。第二次大戦後に生まれ「短い20世紀」の崩壊のなかで新たに研究に取り組もうとする我々「孫」の世代にとって、その研究はパンドラの箱への対応に類するものであろう。開け放った箱から飛び出す夢とそれを引き裂く酸鼻、芳香と異臭、それらの織りなす万華鏡から有意味な像を読み取るには、誠実で持続的な作業が要請されている。それは、落ちゆく岩を再び山頂まで持ち上げ始点に回帰するシジフォスの苦役に類するものかもしれない。
「新しい正統」は、政治の優位性の確認を迫っている。それが、メイリアのようにイデオクラシーを、パイプスのように「家産制」を強調するとしても、我々「孫」の世代は何処から何処へ向かうべきであろうか。政治に向かうべきか、あるいは、社会と文化へ後退し、そこから再び政治と経済へと研究を回帰させるべきであろうか。パイプスの『ロシア革命史』は、類書にはない思想と社会文化へのまとまった叙述と深い洞察があることを忘れてはならない。これは、ヨーロッパ脱出行のなかで、彼が、イタリアで芸術史家を夢見た青春と関係しているのかもしれない。そして、何よりも、彼はカラムジン、ナロードニキ、ストルーヴェの研究者であり、ロシア・インテリゲンツィア論の大家でもあるのだ。社会と文化の多様で多層的な領域でのシジフォスの苦役をへて、現代の神学――これは神ならざる民主主義と市場経済を高唱する――の支配する政治と経済へと攻め戻り、歴史の枠組み全体を考え直す途も開かれているいるように思える。
僕が受け継いだのは空洞の軽いバトンではなく、亜鈴とも覚しき重く走行停止を迫るそれであった。リレーを投げ出すことも頭をよぎったが、快走ならざる迷走のあげく、漸く次に渡せそうである。歴史認識の基底にある「時間」の観念は、残酷である。動植物の世界では、「子」は「親」の世代の資質を最もよく真似、吸収することが最良の生存であろう。人間の世界では、「親」が「子」を自分と同じ存在に育てること、「子」が「親」と同じ人として成育することは、「狂気」に近い。人間の社会は蟻塚ではない、クローンは許されない。「子」は「親」から逸脱し、はみ出し成長することを、人間社会の「時間」は求めている。その意味で、「親」と「子」の間に介在する「時間」は残酷である。カーの「父」、三人の「子」、そして我々「孫」の世代にも、この「時間」の課す残酷さは適用されるように思える。
迷走のはてに、騎士然たらざる奇人と化し、意識も朦朧と混濁を来したようだ。シジフォスに勝さるとも劣らない重く苦しい反復的作業が待ち受けているのであろうか。?!!……
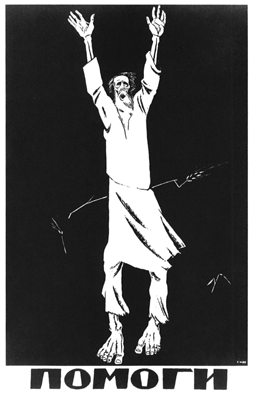 |